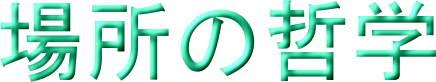Philosophy of Place
人文科学
人文科学総論(編集中)
人文科学に属するものとしては、哲学、心理学、教育学、文学、言語学、芸術学、美学、宗教学、神学、仏教学、歴史学、地理学、考古学、民俗学、文化人類学などがあり、それぞれに学問としての方法論がある。そして、これらが相互に、また、社会科学や自然科学とも、相互に作用し、新たな学際的な学問が展開されつつある。したがって、人文科学の方法論と言っても、一つの共通する方法論が存在するわけではない。ただ、これらは、いずれも人間の意識、行動、言動、技術、文化、風俗などを扱う学問であり、厳密に自然科学的な方法を使って、学問的な客観性を保持することが難しい分野である。そこにあるのは、多様性であり、1人として同じ人は存在しないだけではなく、未だに人間の心理、意識、価値観、認識、言語がどこから生まれてくるのかさえ、分からないのであり、まさしく複雑系の世界である。原子は、どれをとってもみな同じふるまいをするが、人間は、1人として他の人間と全く同じことを考え、同じ行動をする者はいないのである。ここでは一意的な解を得ることは不可能であり、そこに科学ではないと批判を受ける理由がある。
それにも関わらず、これらが学問の対象とされ、人間相互の間に共通する理解を樹立することを可能ならしめているのは、これらを形成する細胞を形作る部分の遺伝子に個人を超えた共通性が存在するからだと考えられる。遺伝子の共通性がタンパク質の共通性を生み、タンパク質の共通性が、人間の認識機能、言語機能、意識形成などに関わる脳細胞の同一性を生み、生後におけるシナプス回路の形成についても、地域的な同質性を持つとき、そこに共通の文化を形作る基礎が生まれる。
また、現実の自然、社会における相互作用の中で、様々な社会的構築物が形成され、それがその地域特有の文化を形作っているのである。そこに共同主観性というものが生まれ、個々人の意思から独立したものを生み出す。それが言語であり、行動様式であり、習慣である。それらの多様性の中に何らかの理論的な一貫性を見いだし、同一性と差異性との結びつきを探求しようとするところに学問としての人文科学が誕生する。
こうした人文科学への場所的なアプローチが二つある。
ひとつは、自然科学的な複雑系理論によるアプローチである。このアプローチは、自然科学の持つ精密性があり、理論負荷性が高く、客観化しやすい。しかし、その半面、自然科学の方法をどこまで人文科学に適用できるのかという問題がある。同じく複雑系と言っても、人間は自然よりも気まぐれである。
これに対する第二のアプローチは、脳科学及びこれに基礎を置く心理学、言語学理論である。人文科学は人間の意識又は無意識に基礎を置いており、これは主として脳とこれに結びつく身体において決定される。ヒトは進化の過程において、五感による外界の分節化に加えて、シンボルによる文化的分節化を発達させており、そこに膨大かつ濃密な意味を産出している。それは延長された表現型としての共同幻想体系を築き上げている。それは一つの文化的体系をなしつつも、多様なバリエーションをそこに生み出しており、更に絶えず、無限に新しいものを産出し続けている。その構造は、現在絶え間なく進展しつつある脳科学及びこれに基礎を置く心理学、言語学の中で、新しい知見をもたらしている。しかし、その半面、ヒトはこれを、そうした共同幻想体系の中でしか表現できないし、認識できないという自己言及性の中にある。こうしたシンボルによる幻想体系の外に出ることはできないのである。それはヒトが共同幻想体系から離れては生きて行くことができないというヒト固有の限界性に由来するのであり、やむを得ないところがある。我々が解明できるのは、言語の限界によって画される西欧の哲学に対し、言語を突き破り、その背後にある実相に迫り、これを何らかの共通するコードによって表現することである。少なくとも、そうすることによって、西欧哲学が解明してきたもの及び今後解明できるものを遙かに上回る成果を人類にもたらす可能性を持っているのである。もっとも、これを共通する言語によって表現したとたんに世界は固定され、分節化された固定的世界に戻ってしまう。その意味に於いて、言語の限界が世界の限界であるとするヴィトゲンシュタインは正しいのであるが、人類に共通する五感を利用した非言語的コードを用いれば、ヒトは、言語的コードの背後にある多様性を手に入れることもできるのである。